ホーム »
適切な意思決定支援に係る指針
Ⅰ.総論
1.基本理念
ノーマライゼーション理念の浸透や障害者の権利擁護が求められるなかで、障害者の自己決定の尊重に基づいて支援することの重要性を認識することである。
枚方総合発達医療センター(以下「センター」という。)は、「愛情を持った療育の中で、しっかり見つめる心と体。私たちは全人療育の向上を目指します。」の理念の基、 ①生命の保持、保全 ②健康で快適な規則正しい療育生活 ③環境への適応と心身の自立 ④全人療育の向上 を目標に、利用者の尊厳を守り、安全安心な医療、介護を提供している。当センターでは、意思疎通が困難な利用者が大半を占めているため、利用者の日々の日常生活等の関わりから、その刺激や反応より利用者の自己決定につながる情報を集め対応していく必要がある。したがって、利用者に関わる職員は、本人の意思を尊重しようとする態度で接し、利用者と良い信頼関係を築いていくことが望まれる。
2.意思決定支援とは
自ら意思を決定することに困難を抱える利用者が、日常生活や社会生活に関して自らの意思が反映された生活を送ることができるように、可能な限り本人が自ら意思決定できるよう支援し、本人の意思の確認や意思及び選好を推定し、支援を尽くしても本人の意思及び選好の推定が困難な場合には、最後の手段として本人の最善の利益を検討するためにセンター職員が行う支援の行為及び仕組みをいう。
3.意思決定を構成する要素
障害者の意思決定を構成する要素としては、次の三つが考えられる。
(1)本人の判断能力
本人の障害による判断能力の程度は、意思決定に大きな影響を与える。
例えば、何を食べるか、何を着るかといった日常生活における意思決定は可能だが、施設から地域生活への移行等住まいの場の選択については意思決定に支援が必要であるといった事例が考えられる。意思決定を進める上で、本人の判断能力の程度についての慎重なアセスメントが重要となる。
(2)意思決定支援が必要な場面
意思決定支援は、次のような場面で必要とされることが考えられる。
ア 日常生活における場面
日常生活における意思決定支援の場面としては、例えば、食事、衣服の選択、外出、排せつ、整容、入浴等基本的生活習慣に関する場面の他、複数用意された余暇活動プログラムへの参加を選ぶ等の場面が考えられる。日頃から本人の生活に関わるセンターの職員が場面に応じて即応的に行う直接支援の全てに意思決定支援の要素が含まれている。
日常生活における場面で意思決定支援を継続的に行うことにより、意思が尊重された生活体験を積み重ねることになり、本人が自らの意思を他者に伝えようとする意欲を育てることにつながる。
日常生活における支援場面の中で、継続的に意思決定支援を行うことが重要である。
イ 社会生活における場面
障害者総合支援法の基本理念には、全ての障害者がどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられない旨が定められていることに鑑みると、自宅からグループホームや入所施設等に住まいの場を移す場面や、入所施設から地域移行してグループホームに住まいを替えたり、グループホームの生活から一人暮らしを選ぶ場面等が、意思決定支援の重要な場面として考えられる。体験の機会の活用を含め、本人の意思確認を最大限の努力で行うことを前提に、センター職員、家族や、成年後見人等の他、必要に応じて関係者等が集まり、判断の根拠を明確にしながら、より制限の少ない生活への移行を原則として、意思決定支援を進める必要がある。
(3)人的・物理的環境による影響
意思決定支援は、本人に関わる職員や関係者による人的な影響や環境による影響、本人の経験の影響等を受ける。
例えば、意思決定支援に関わる職員が、本人の意思を尊重しようとする態度で接して いるかどうかや、本人との信頼関係ができているかどうかが影響することが考えられる。また、意思決定の場面に立ち会う家族等の関係者との関係性も影響を与える可能性がある。
環境に関しては、初めての慣れない場所で意思決定支援が行われた場合、本人が過度に緊張してしまい、普段通りの意思表示ができないことも考えられる。また、サービスの利用の選択については、体験利用を活用し経験に基づいて選択ができる方法の活用など経験の有無によっても影響されることが考えられる。
4.意思決定支援の基本的原則
意思決定支援の基本的原則を次のように整理する。
(1)本人への支援は、自己決定の尊重に基づき行うことが原則である。本人の自己決定にとって必 要な情報の説明は、本人が理解できるよう工夫して行うことが重要である。また、幅広い選択肢から選ぶことが難しい場合は、選択肢を絞った中から選べるようにしたり、絵カードや具体物を手がかりに選べるようにしたりするなど、本人の意思確認ができるようなあらゆる工夫を行い、本人が安心して自信を持ち自由に意思表示できるよう支援することが必要である。
(2)職員等の価値観においては不合理と思われる決定でも、他者への権利を侵害しないのであれば、その選択を尊重するよう努める姿勢が求められる。
また、本人が意思決定した結果、本人に不利益が及ぶことが考えられる場合は、意思決定した結果については最大限尊重しつつも、それに対して生ずるリスクについて、どのようなことが予測できるか考え、対応について検討しておくことが必要である。例えば、疾病による食事制限があるのに制限されている物が食べたい、生活費がなくなるのも構わず大きな買い物がしたい、一人で外出することは困難と思われるが、一人で外出がしたい等の場合が考えられる。
それらに対しては、食事制限されている食べ物は、どれぐらいなら食べても疾病に影響がないのか、あるいは疾病に影響がない同種の食べ物が用意できないか、お金を積み立ててから大きな買い物をすることができないか、外出の練習をしてから出かけ、さらに危険が予測される場合は後ろから離れて見守ることで対応することができないか等、様々な工夫が考えられる。
リスク管理のためには、事業所全体で取り組む体制を構築することが重要である。また、リスク管理を強調するあまり、本人の意思決定に対して制約的になり過ぎないよう注意することが必要である。
(3)本人の自己決定や意思確認がどうしても困難な場合は、本人をよく知る関係者が集まって、本人の日常生活の場面や事業者のサービス提供場面における表情や感情、行動に関する記録などの情報に加え、これまでの生活史、人間関係等様々な情報を把握し、根拠を明確にしながら障害者の意思及び選好を推定する。
本人のこれまでの生活史を家族関係も含めて理解することは、職員が本人の意思を推定するための手がかりとなる。
5.最善の利益の判断
本人の意思を推定することがどうしても困難な場合は、関係者が協議し、本人にとっての最善の利益を判断せざるを得ない場合がある。最善の利益の判断は最後の手段であり、次のような点に留意することが必要である。
(1)メリット・デメリットの検討
最善の利益は、複数の選択肢について、本人の立場に立って考えられるメリットとデメリットを可能な限り挙げた上で、比較検討することにより導く。
(2)相反する選択肢の両立
二者択一の選択が求められる場合においても、一見相反する選択肢を両立させることができないか考え、本人の最善の利益を追求する。
例えば、健康上の理由で食事制限が課せられている人も、運動や食材、調理方法、盛り付け等の工夫や見直しにより、可能な限り本人の好みの食事をすることができ、健康上リスクの少ない生活を送ることができないか考える場合などがある。
(3)自由の制限の最小化
住まいの場を選択する場合、選択可能な中から、障害者にとって自由の制限がより少ない方を選択する。
また、本人の生命または身体の安全を守るために、本人の最善の利益の観点からやむを得ず行動の自由を制限しなくてはならない場合は、行動の自由を制限するより他に選択肢がないか、制限せざるを得ない場合でも、その程度がより少なくて済むような方法が他にないか慎重に検討し、自由の制限を最小化する。
その場合、本人が理解できるように説明し、本人の納得と同意が得られるように、最大限の努力をすることが求められる。
6.センター以外の視点からの検討
意思決定支援を進める上で必要となる本人に関する多くの情報は、本人にサービス提供しているセンターが蓄積している。しかし、センターはサービスを提供する上で、制度や組織体制による制約もあるため、それらが意思決定支援に影響を与える場合も考えられることから、そのような制約を受けないセンター以外の関係者も交えて意思決定支援を進めることが望ましい。本人の家族や知人、成年後見人等の他、ピアサポーターや基幹相談支援センターの相談員等が、本人に直接サービスを提供する立場とは別の第三者として意見を述べることにより、様々な関係者が本人の立場に立ち、多様な視点から本人の意思決定支援を進めることができる。
7.成年後見人等の権限との関係
法的な権限を持つ成年後見人等には、法令により財産管理権とともに身上配慮義務が課されている。一方、センターが行う意思決定支援においても、入所施設からの地域移行等、成年後見人等が担う身上配慮義務と重複する場面が含まれている。意思決定支援の結果と成年後見人等の身上配慮義務に基づく方針が齟齬をきたさないよう、意思決定支援のプロセスに成年後見人等の参画を促し、検討を進めることが望ましい。
なお、保佐人及び補助人並びに任意後見人についても、基本的な考え方としては、成年後見人についてと同様に考えることが望まれる。
Ⅱ.各論
1.意思決定支援の枠組み
意思決定支援の枠組みは、意思決定支援責任者の配置、意思決定支援会議の開催、意思決定の結果を反映したサービス等利用計画・個別支援計画(意思決定支援計画)の作成とサービスの提供、モニタリングと評価・見直しの5つの要素から構成される。このようにして作成されたサービス等利用計画・個別支援計画(意思決定支援計画)に基づき、日頃から本人の生活に関わるセンターの職員が、全ての生活場面の中で意思決定に配慮しながらサービス提供を行う。
(1)意思決定支援責任者の役割
意思決定支援を適切に進めるため、当センターは意思決定支援責任者を配置する。
意思決定支援責任者はサービス管理責任者が重複してその役割を担う。
ア 意思決定支援責任者の役割
意思決定支援計画作成に中心的に関わり、意思決定支援会議を企画・運営するなど意思決定支援の枠組みを作る役割を担う。
① 本人の希望するサービスを提供するためのサービス等利用計画や個別支援計画を作成する前提として、意思決定支援を適切に進めるため、本人の意思の確認・推定や本人の最善の利益の検討の手順や方法について計画する。
② 意思決定支援を進める上で必要となる事項について検討する。
・本人の意思決定支援に参考となる情報や記録を誰から収集するのか
・意思決定支援会議の参加者の構成
・意思を表出しやすい日時や場所の設定
・絵カードの活用等本人とのコミュニケーション手段の工夫等
③ 本人の意思及び選好、判断能力、自己理解、心理的状況、これまでの生活史等本人の情報、人的・物理的環境等を適切にアセスメントするために以下の方法で情報を収集する。
・意思決定を必要とする事項について本人から直接話しを聞く
・日常生活の様子を観察する
・体験の機会を通じて本人の意思を確認する
・関係者から情報を収集する
イ 意思決定支援会議の開催
意思決定支援会議とは、本人参加の下で、アセスメントで得られた意思決定が必要な事項に関する情報や意思決定支援会議の参加者が得ている情報を持ち寄り、本人の意思を確認したり、意思及び選好を推定したり、最善の利益を検討する仕組みである。
① 本人の意思を当センターだけで検討するのではなく、家族や、成年後見人等の他、必要に応じて関係者等の参加を得ることが望ましい。
② 「サービス担当者会議」や「個別支援会議」と一体的に実施する。
ウ 意思決定が反映されたサービス等利用計画や個別支援計画(意思決定支援計画)の作成とサービスの提供
① 意思決定支援によって確認又は推定された本人の意思や、本人の最善の利益と判断された内容を反映したサービス等利用計画や個別支援計画(意思決定支援計画)を作成し、本人の意思決定に基づくサービスの提供を行う。
② 体験を通じて本人が選択できたり、体験中の様子から本人の意思の推定が可能となったりするような場合は、そのようなアセスメント方法を意思決定支援計画の中に位置付ける。 例) A. 院外活動に消極的だった利用者が、外出し観劇したことで、個別支援活動の院外活動に積極的になった。
B. 普段は吸い飲みで水分摂取している利用者が、誕生日のお祝いにヨーグルト飲料をストローで提供したところ飲むことができた。職員から賞賛され味も気に入った様子で、それが喜びに繋がった。それ以降、誕生日のお祝いでは、市販のストロー付きの飲み物を楽しんでいる。
C. もともと音楽に興味がとてもある利用者が、ご家族から誕生日プレゼントにデッキ購入してもらった。その後、職員が操作しているのを見て、回すタイプの音量を指を曲げて引っかけるようにして回し操作できるようになった。
D. 上下の着衣を破ってしまう利用者に、上下服を2着ずつ本人の目の前に提供し、本人が選択できるように配慮した。すると自ら選択した衣類は破ることなく服を着続けられるようになった。自身で選択することで納得されたと考える。
エ モニタリングと評価及び見直し
① 意思決定支援を反映したサービス提供の結果をモニタリングし、評価を適切に行う。
② 次の支援でさらに意思決定が促進されるよう見直す。
③ モニタリングと評価及び見直しについては、意思決定の結果を反映したサービス等利用計画や個別支援計画に基づくサービス提供を開始した後の本人の様子や生活の変化について把握する。
④ その結果、本人の生活の満足度を高めたか等について評価を行う。
⑤ それらのモニタリング及び評価の情報を記録に残こすことで、次に意思決定支援を行う際の有効な情報とし、見直しにつなげる。
*意思決定支援は、Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Act(改善)で構成されるいわゆるPDCAサイクルを繰り返すことによって丁寧に行う
2.意思決定支援における意思疎通と合理的配慮
本人との意思疎通を丁寧に行うことによって、本人と支援者とのコミュニケーションが促進され、本人が意思を伝えようとする意欲が高まり、本人が意思決定を行いやすい状態をつくることができる。 (1)意思決定に必要だと考えられる情報を本人が十分理解し、保持し、比較し、実際の決定に活用できるよう配慮をもって説明する。 (2)決定したことの結果、起こり得ること等を含めた情報を可能な限り本人が理解できるよう、意思疎通における合理的配慮を行う。
3.意思決定支援の根拠となる記録の作成
意思決定支援を進めるためには、本人のこれまでの生活環境や生活史、家族関係、人間関係、嗜好等の情報を把握しておくことが必要である。家族も含めた本人のこれまでの生活の全体像を理解することは、本人の意思を推定するための手がかりとなる。
(1)本人の日常生活における意思表示の方法や表情、感情、行動から読み取れる意思について記録・蓄積し、今後の意思決定支援に役立てる。
① 本人の意思を読み取ったり推定したりする際に根拠を持って行う。
② 客観的に整理や説明ができないような「刺激と反応」を記録に残し、積み上げていくことは、障害者の意思決定を支援する上で重要な参考資料になる。
*本人が意思決定することが難しい場合でも、「このときのエピソードには、障害者の意思を読み取る上で重要な『刺激と反応』が含まれている」という場合がある。
③ 意思決定支援の内容と結果における判断の根拠やそれに基づく支援を行った結果がどうだったかについて記録しておく。
4.職員の知識・技術の向上
意思決定支援の意義や知識の理解及び技術等の向上のため、職員へ院内外研修を受講する。
5.関係者、関係機関との連携
意思決定支援責任者は、当センター、家族や成年後見人等の他、関係者等と連携して意思決定支援を進めることが重要である。
関係者等と連携した意思決定支援の枠組みの構築には、協議会を活用する等、地域における連携の仕組みづくりを行い、意思決定支援会議に関係者等が参加するための体制整備を進めることが必要である。
意思決定支援の結果、社会資源の不足が明らかとなった場合等は、協議会で共有し、その開発に向けた検討を行ったり、自治体の障害福祉計画に反映し、計画的な整備を進めたりするなど、本人が自らの意思を反映した生活を送ることができるよう取り組みを進めることが求められる。
6.本人と家族等に対する説明責任等
(1) 意思決定支援計画、意思決定支援会議の内容についての丁寧な説明を行う。
① 説明者は、サービス管理責任者 病棟師長 主任 副主任とする。
② 本人、家族に理解しやすいように工夫し行うこと
(2)苦情解決の手順等について
① 当センターの苦情解決について
・苦情解決責任者のもと当センターでは苦情申出窓口を設置し、苦情受付担当者が随時受け付けている(詳細は福祉サービスに関する苦情解決事業実施要綱参照)
・意思決定支援に関する苦情についても、福祉サービスに関する苦情解決事業実施要綱に従った対応を行い、意思決定支援責任者は、苦情受付担当者、苦情解決責任者、第三者委員と協働して対応に当たる。
② 秘密保持と個人情報の保護について
・意思決定支援に関わったセンター職員、成年後見人等や関係者等は、職を辞した後も含めて、業務上知り得た本人やその家族の秘密を保持しなければならない。(個人情報保護規定参照)
7.終末期の意思決定支援
人生の緒最終段階における意思決定支援については、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」の趣旨に則り、利用者の意思が確認できない場合であって、家族等が利用者の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、利用者にとっての最善の方針を取ることを基本とする。家族等が利用者の意思を推定できない場合には、利用者にとって何が最善であるかについて、利用者に代わるものとして家族等と十分に話し合い、利用者にとっての最善の方針を取ることを基本とする。時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行う。家族がいない場合または家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、利用者にとっての最善の利益は何かを関係スタッフ・多職種で話し合い(倫理カンファレンス)、チームとしての合意形成を図る。
*倫理カンファレンスの際には、人生曲線のどの地点かの認識を共有し、ジョンセンの四分割表を用いて情報の整理をして、それぞれの要素を確認検討する。
*家族ではない後見人については、医療について判断する立場ではないが、施設や医療機関からの方針が利用者の権利を尊重しているかどうかという点では意見を述べることができる立場にあるため、家族がいない場合には、後見人にもできるだけ、検討の過程で参加していただくこととする。
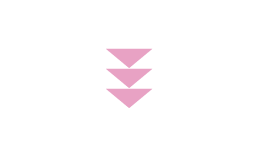
必要時、倫理コンサルテーションチームが倫理カンファレンスなどについて支援する。
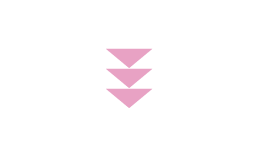
倫理カンファレンスの結果、倫理的に問題がないか等確認が必要な時は、倫理委員会の承認を得ておく。(「枚方総合発達医療センター利用者の終末期医療に関するガイドライン」参照)
附則
この指針は、令和6年10月1日から施行する。
